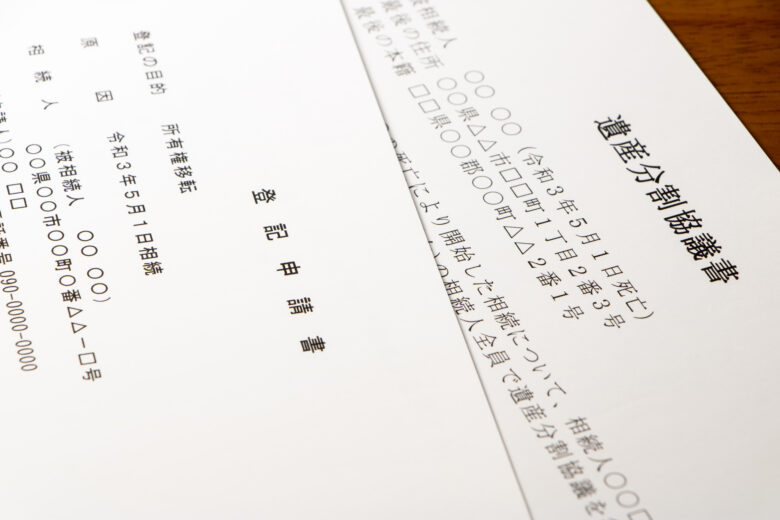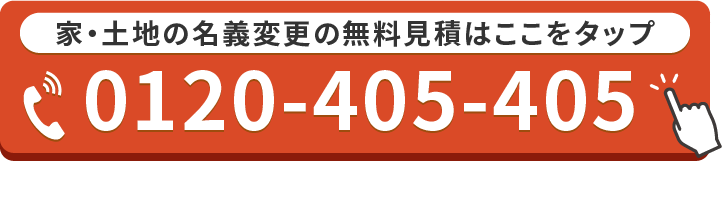【相続登記の費用】自分でやると?司法書士に頼むと? 費用を抑える方法は?現役司法書士がズバリ解説!
2024.02.08 相続登記(名義変更)
故人から土地や建物を相続したとしても、その不動産の名義は勝手に変わるわけではなく、不動産の名義を変更するために、法務局に相続登記の申請をする必要があります。
そして相続登記を申請するのにはお金がかかります。
この記事では土地や建物などの不動産の相続登記をする際には、
「どのような費用がどれくらいかかるのか?」
「自分でやる場合の費用は?」
「専門家に依頼する場合には、どのくらいの値段がするのか?」
ということについて詳しく説明しております。これから相続登記の申請を検討されている方は、この記事で相続登記にかかる費用を確認されることをおすすめします。
目次
1.相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなってしまった場合、その不動産の所有者の名義を、相続によって取得した方の名義に変更する手続きです。
これまで、相続登記の申請は必須ではありませんでしたが、法の改正により義務化されることになりました。※1
そのため、不動産を相続によって取得した場合に、滞りなく登記申請準備・手続きを進められるよう必要な費用・書類について確認していきましょう。
※1 令和6(2024)年4月1日以降に相続登記の申請が義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。
また、令和6(2024)年4月1日より前に相続が発生した場合でも、令和6(2024)年4月1日から3年以内の登記申請が必要となります。
相続登記の義務化について詳しく知りたい方は、【法務局の[相続登記の義務化]が分かる!2024年4月以降の罰則や対策をかんたん解説!】の記事で詳しく解説しておりますので、こちらも是非ご参照下さい。
2.相続登記の費用
相続登記の申請に必要な費用は、必須なものとして登録免許税と必要書類の取得費用が、必須でないものとして司法書士に依頼した場合に生じる司法書士報酬があります。
登録免許税
登録免許税とは、登記を申請する際に納めなければならない税金です。
相続登記の税額は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です(100円以下は切り捨て)。
例 固定資産時評価額が1000万円であれば4万円
固定資産時評価額が3000万円であれば12万円
必要書類の取得費用
相続登記を申請する際、申請書には、亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本や相続人の住民票等、添付しなければならない書類があり、それらの取得には以下の通り発行手数料等がかかります。
また、これらの書類を郵送で取得する場合は、合わせて郵送料などがかかります。
1通当たりの手数料 | |
戸籍謄本 | 450円 |
除籍謄本 | 750円 |
住民票 | およそ300円~500円 |
固定資産税評価証明書 | およそ300円~400円 |
印鑑証明書 | およそ200円~300円 |
司法書士に依頼する場合の報酬
司法書士等の専門家に相続登記の代理申請を依頼する場合は報酬が必要となります。
不動産や相続人の数や相続の内容にもよりますが、報酬額の相場は7万円~15万円です。報酬規程は司法書士事務所によって異なりますので、後のトラブルを避けるためにも、相続登記の依頼する際には必ず事前に見積もりをしてもらい具体的な金額を確認しましょう。
相続をスマートに!面倒な相続登記は安心定額「スマそう-相続登記-」にお任せください!
3.相続登記の費用を抑えるには
上記の通り、相続登記の申請には意外と費用がかかります。これらを抑える方法はあるのでしょうか。
登録免許税
登録免許税を抑えるには免税措置の適用を受ける必要があり、以下のどちらかにでも当てはまればその適用を受けることができます。
①相続により土地を取得した方が相続登記をせずに亡くなった場合
この場合に相続登記を申請する場合は、過去の相続分と合わせて2回分の相続登記を申請する必要がありますが、過去の相続登記分の登録免許税については免税措置を受けられます。
例 祖母Aの土地を父Bが相続したが、相続登記を申請する前に父Bが亡くなり、息子Cが土地を相続したケースの場合、祖母Aから父Bへの相続登記にかかる登録免許税は免税される。
②不動産の評価額が100万円以下の土地である場合
ただし、免税措置が適用される期間は令和7(2025)年3月31日までに限り、免税措置の適用を受けるには、登記申請書に免税の根拠となる法令の条項を記載しなければなりません。
②の場合の記載例 「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
②の場合の記載例 「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」
登録免許税の免税について詳しく知りたい方は、【相続登記の登録免許税が免税になるケースは?手続き方法や期限は?】の記事で詳しく解説しておりますので、こちらも是非ご参照下さい。
必要書類の取得費用
亡くなった方が生前に本籍地を複数の市区町村にまたがって転籍していたケースでは、戸籍謄本等の必要書類は複数の役所で取得することになります。当事務所で相続登記の依頼を受ける方の多くがこのケースにあてはまっております。その場合、役所が遠隔地にあると郵送取得の必要があるため、郵送代や小為替手数料などが余分にかかります。
しかし、令和6年3月1日以降は戸籍謄本の広域交付制度を利用することにより、自宅や勤務地の最寄りの市区町村の窓口で全国各地の戸籍謄本を取得することができるため、必要書類の取得費用を抑えることができます。
参考:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
また、マイナンバーカードを利用したコンビニ等における証明書等の交付サービスであれば、戸籍謄本等を、窓口での交付より安く取得することができます。
取得できる必要書類については自治体により異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
司法書士に依頼する場合の報酬
登記費用を抑えるには、司法書士に依頼せず自身で登記申請を行う必要があります。詳しくは本記事の後半にも記載しますが、簡単な相続登記であり、かつ費用を少しでも抑えたいのであれば自身で手続きを進めることも可能です。ただし、必要書類を自分集めなければならず、遺産分割協議書や相続登記の申請書を自分で調べながら作成しなければならないというデメリットがあります。
また、司法書士に依頼する場合であっても、必要書類の収集などの一部の作業を自分で行うことにより、司法書士事務所によっては報酬を安くしてくれる可能性もあります。
4.相続時の必要書類及び取得方法
相続登記を申請する際、申請書はもちろんのこと他にも必要な書類が多くあります。
なお、登記申請書に添付する書類は、コピーではなく原本が必要です。
①必ず必要な書類
1 相続登記の申請書
申請人側で作成する必要があります。
法務局に申請書の様式と記載例が公開されているので、どのように記載すればいいかわからない場合は参考にしましょう。
法務局「不動産登記の申請書様式について」
2 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本
取得先は役所です。
3 被相続人の出生から住民票除票又は本籍地が記載された戸籍の附票
取得先は役所です。
4 法定相続人全員の戸籍謄本
取得先は役所です。
5 不動産を取得する相続人の住民票
取得先は役所です。
6 固定資産税評価証明書
取得先は役所です。
7 相続関係説明図
被相続人の相続関係を示した説明図を作成する必要があります。
こちらも上記の法務局のHPに記載例が公開されているため参考にしましょう。
②遺産分割協議をした場合に必要な書類
遺産分割協議をした場合は、上記の①に加え、以下の書類が必要になります。
1 遺産分割協議書
申請人側で作成する必要があります。
2 法定相続人の印鑑証明書
遺産分割協議書に捺印した印鑑のものが必要で、取得先は役所です。
③遺言書に従って登記をする場合
被相続人の遺言書に従って登記をする場合は、上記の②の代わりに遺言書が必要になります。
なお、自筆証書遺言が存在する場合、中身の確認の前に家庭裁判所に提出し、遺言書の偽造防止等を行うための検認という手続きが必要です。なお、公正証書遺言や法務局保管制度を利用した自筆証書遺言であれば、家庭裁判所の検認手続きは不要です。
相続登記の必要書類について詳しく知りたい方は、【法務局の[相続登記の必要書類一覧]をかんたん解説!】の記事で詳しく解説しておりますので、こちらも是非ご参照下さい。
5.相続登記を自分で行う場合の流れ
相続登記の申請は、司法書士等の専門家に依頼せず、自身で行うこともできます。
それでは、自身で行う場合はどの様な流れになるのでしょうか。相続登記のやり方とおおまかな流れを確認しましょう。
相続財産の確定
まずは相続財産となる不動産の確認が必要です。
被相続人が所有していた不動産の有無の確認は、固定資産納税通知書や不動産の権利証を探すと良いでしょう。それらが無ければ、役所で固定資産評価証明書や名寄帳を取得することにより、被相続人が所有していた不動産の有無が確認できます。
相続人を確定させる
相続財産に不動産があることが判明したのであれば、法定相続人を確定させる必要があります。
たとえ単独相続であったとしても、ほかに相続人がいないことを確定させる必要があるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本を収集し、認識できていない相続人がいないか確認しましょう
遺言書が見つかった場合
被相続人が自筆証書遺言を残していた場合、中身を開封する前に、家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを受けてください。
遺産分割協議書の作成
法定相続人が複数存在し、法定相続分でない持ち分とする場合は、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書の作成に当たっては、必ずしも現実に相続人全員が集まる必要はありません。一部の相続人が遠方に存在する、多忙によるなどで現実に集まることが難しい場合は、あらかじめ電話等で話し合い、協議書を郵送して署名捺印をしてもらったうえで返送してもらう、という流れでも大丈夫です。
必要書類の収集・作成
本記事の4項で記載した通り、相続登記を申請するためには、戸籍謄本や住民票の取得が必要です。
遠方の役所から戸籍等を取得する場合は、郵送での請求も可能です。
書類に有効期限はありませんが、相続人の戸籍謄本については、相続が開始された後(被相続人が亡くなった以降)に取得する必要があります。
収入印紙の準備
登記申請書には登録免許税分の収入印紙を割り印せずに貼り付けてください。
印紙の額は、不動産の評価額に0.4を乗じ、100円未満を切り捨てた額です。
相続登記の申請
以上の準備が終わったら、法務局の窓口に相続登記の申請を行います。
無事、登記が受理されれば、登記識別情報通知という不動産の権利書代わりになるものが通知されるので、厳重に保管してください。
6.相続登記を「スマそう」で行う場合
これまで記載した通り、相続登記の申請には必要書類の収集や書類作成と、準備に手間がかかります。報酬が多少かかっても、時間や手間をかけず、故人が残してくれた大切な不動産の名義変更をミスなく行いたいという方は、司法書士への代理申請の依頼を検討するのが良いでしょう
当事務所が運営する「スマそう-相続登記-」では、上記の手続きは全てお任せいただくことが可能です。また、報酬についても皆様が安心して相続登記を依頼できるように、定額79,800円(税込87,780円/1管轄・実費別/分割払い可)というリーズナブルな価格で承っております。
7.まとめ
相続登記の申請は、単独相続である等、相続関係が複雑でなく、時間がある方で少しでも費用を抑えたい場合は自身で申請するのがおすすめです。
過去の分もさかのぼって相続登記をしなければならない、相続関係が複雑であるため相続人の特定や書類の収集が困難である場合などや、自身で手続き進める時間がない場合や自信がない場合には、まずは司法書士にご相談されることをおすすめします。
司法書士法人みどり法務事務所では相続でお悩みの皆様に、安心でリーズナブルな相続を済ませて頂くために、定額の不動産の名義変更サービス「スマそう-相続登記-」をはじめとする遺産相続に関する各種サービス(ゆうちょ・みずほ・三井住友・三菱UFJ、りそななどの各金融機関の相続にともなう預貯金の解約払戻し、その他相続に関する裁判所提出書類作成サポートなど)をおこなっています。また、電話や来所での相続相談は無料で承っております。相続に関してお悩みの方はまずはお気軽にお電話ください。
関連記事
人気記事
新着記事
 相続登記の
相続登記の